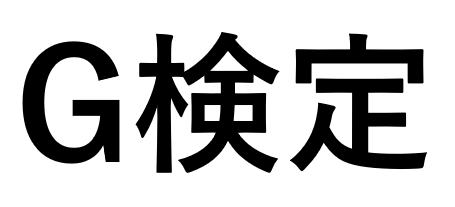記事の概要
少し前になってしまいましたが、G検定を受けました。
この記事ではG検定を受けようか悩んでいる人に向けて、G検定を取得する中でどのようなことが学べるのかを自分の経験からまとめています。
結論としては、AIの仕組みや歴史を学びたい人やAIを使う上での注意点を知りたいという人におすすめかなと思っています。
G検定とは
G検定とは、JDLAが運営しているAI・ディープラーニングの活⽤リテラシー習得のための検定試験です。
JDLAとは正式名称Japan Deep Learning Association、日本ディープラーニング協会のことで「ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上」を目的として設立された組織でG検定の他にもE資格やGenerative AI Testといった資格を運営しています。
G検定では、AI・ディープラーニングについて体系的に学ぶことができ、特にAI・ディープラーニングに関する歴史や活用方法、また活用する際の法や倫理についてフォーカスされています。
やったこと
G検定を取得する中で学んだことの前に、私がG検定を受験するためにやったことを簡単に振り返っておきます。
■前提
私はもともと学生時代に情報系の学部であったことや、当時は深層学習が流行っていたこともありG検定の範囲に関しての知識は少しある状態でした。一方で、ちょっと試す程度だったので法律や倫理については今回が初めてでした。
■下調べ
公式サイトで試験日時や申込期限、試験範囲を調べたり、ネット上に投稿されている受験記を読んだりして、スケジュール感・学習範囲・学習ポイントを整理しました。
■学習
問題集をひらすら解きました。そして、間違えた箇所や各選択肢の解説を読みながら知らない知識を補っていくという流れです。各単元が終わった時点で、ネット記事やYouTubeなどで復習してイメージを固めました。
学んだこと
■AIの仕組みや歴史
問題集の問題がすごく体系的にまとまっているなと感じました。
体系的に学習できるのは資格学習の良いところですが、特にそれぞれのモデルがどのように発展していったのかを追えるような構成になっていたのが面白かったです。私が学生時代に学習していたときはCNNやRNN、LSTMのような基本的な構成を学んだあとは個別に有名なモデルを触ってみるという感じだったので、それぞれの繋がりが整理されていて良かったです。
■AIを使う上での注意点
企業で活動する上で法律や倫理の話は大事だと感じました。
普段は「課題をどのように解決するか」に注目するので、法律的に倫理的に問題ないかという観点は漏れがちです。ケース形式で違反するかどうかを見ていくことで、具体的に気をつける場面がイメージしやすかったです。生成AIに関する法律や倫理についてはまだ過渡期だと思いますが、定期的にチェックしたほうが良いなと感じるきっかけになりました。
最後に
■G検定を気になっている方へ
G検定は実装の話とは少し離れているかもしれませんが、深層学習の歴史や使用する上での注意点を体系的に学ぶことができるため、これからAIを学びたい人やAIを使って仕事上の課題に取り組もうという人におすすめです。社内でも、どのようなAIが世の中にはあって、どのように使い分けたりどのような点に注意をしたほうが良いのかについての共通認識として活用しています。
■受験結果
ちなみに結果は合格でした。
2025#1を受験したのですが120分160問で、時間には余裕があるように感じました。
これから受験される方は頑張ってください。